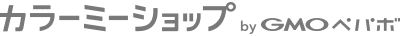- •Ř°ľ•ŗ
- > ņų§Š°¶Ņ•§Í
- > Ń“…ŖŚňńŐ

Ń“…ŖŚňńŐ
Ń“…ŖŚňńŐ° §Į§ť§∑§≠§ņ§ů§ń§¶°ň§Ō°Ę§ę§ń§∆§ő§§Ńū§őĽļ√Ō°¶Ń“…Ŗ§«Ņ•§ť§ž§ŽŚį›Ŗ§«§Ļ°£
≤¨Ľ≥ł©Ń“…ŖĽ‘§Ō°ĘĻĺłÕĽĢ¬Ś§ę§ť§§Ńū§őĽļ√Ō§»§∑§∆√ő§ť§ž°ĘĺŲ…ŧ §…§ő§§ŃūņĹ… §őņłĽļ§¨ņĻ§ů§«§∑§Ņ°£
Őņľ£§ę§ť¬ÁņĶ§ň§ę§Ī§∆§Ō°Ę≤÷šß° §Ō§ §ŗ§∑§Ū°ň§¨≥§≥į§ňŅ۬Ņ§ĮÕĘĹ–§Ķ§ž§ř§∑§Ņ§¨°Ę
ĺľŌ¬ĹťīŁ§ň§ŌŅͬŗ§őīŪĶ°§ňīŔ§Í§ř§Ļ°£
§Ĺ§≥§«°Ę≤÷šß§ň¬Ś§Ô§Ž§§ŃūņĹ… §»§∑§∆°ĘŌ¬Õőņř√Ô§őŇŲĽĢ§ő∆Łň‹§ő Ž§ť§∑§ňĻÁ§§°Ę
≥§≥į§ň§‚ļő§Í∆Ģ§ž§ť§ž§Ž§‚§ő§»§∑§∆ĻÕį∆§Ķ§ž§Ņ§ő§¨°Ę
Ń“…ŖŚňńŐ§őŃįŅ»§«§Ę§Ž∂‚«»Ņ•° §≠§ů§—§™§Í°ň§«§∑§Ņ°£
Ń“…Ŗ§Úň¨§ž§ŅŐÝĹ°ĪŔ§Ō°Ę§≥§őńѧ∑§§Ņ• ™§ňŐ‹§ÚőĪ§Š°ĘņųŅßĻ©∑›≤»°¶∂‹¬Űý§≤ū§ň•«•∂•§•ů§ÚįÕÕÍ°£
§Ĺ§∑§∆Ņ∑§Ņ§ň°÷Ń“…ŖŚňńŐ°◊§»Őĺ…’§ĪĻ≠§Įĺ“≤ū§∑§ř§∑§Ņ°£
ŐĪ∑›į¶Ļ•≤»§Ú√śŅī§ň°ĘĻ‚§§ŅÕĶ§§Úł∆§”§ř§Ļ°£

ņÔłŚ§‚Ķ°≥£≤ŧĽ§ļ¬Á∑Ņ§őĶ°§ň§Ť§ŽľÍĽŇĽŲ§¨į›Ľż§Ķ§ž°Ę
ĺľŌ¬30〜40«Įļʧňļ«ņĻīŁ§Ú∑ř§®§ř§Ļ§¨°Ę§Ĺ§őłŚ§ŌŅͬŗ°Ę
ĺľŌ¬61«Į§ň§ŌņłĽļ§¨Ň”ņš§®§∆§∑§ř§§§ř§∑§Ņ°£
§Ĺ§őłŚ°Ę Ņņģ4«ĮļʧňŃ“…ŖŚňńŐ§Úļ∆∂ŧ∑°ĘĽń§ĻľŤ§ÍŃ»§Ŗ§¨√ŌłĶ§«Ļ‚§ř§Í§ř§Ļ°£
§Ĺ§őļӧ;ͧ»§∑§∆«ÚĪ©§őŐū§¨ŇŲ§Ņ§√§Ņ§ő§¨°ĘłĹļŖ§őļӧ;Ͱ¶¬ŪĽ≥Õļįž§Ķ§ů§«§Ļ°£
įžŅÕ§«Ńī§∆§őĻ©ńݧڧ≥§ §∑§ř§Ļ°£

őĘ√Ō§ň§Ō°Ę§§Ńū§ÚĽś•∆°ľ•◊§«ī¨§§§Ņ§‚§ő°Ę
…Ĺ√Ō§ň§Ō°Ęň„§»•ž°ľ•Ť•ů§őļģň¬§ň§Ť§Ž•Í•ů•įĽŚ§¨Õ—§§§ť§ž§ř§Ļ°£

§§Ńū§ÚŅŰň‹¬ę§Õ§Ņ§‚§ő§¨Ľś§«ī¨§ę§ž°ĘőĘ√Ō§ň§ §√§∆§™§Í°ĘҨŇŔ§ňńŐĶ§ņ≠§¨ ›§Ņ§ž§∆§§§ř§Ļ°£
…Ĺ√Ō§Ō°ĘľęŃ≥Ń«ļŗ§«§Ķ§ť§√§»§∑§Ņ»©Ņ®§Í§«°ĘŅ®§ÍŅī√Ō§‚§Ť§§°£
≤∆§Ōő√§∑§Į°ĘŇŖ§Ō≤Ļ§ę§Ŗ§¨ī∂§ł§ť§ž§Ž°Ę§ř§Ķ§ň∆Łň‹§őĶ§łű°¶…ųŇŕ§ę§ťņł§ř§ž§Ņ…Ŗ ™§«§Ļ°£

ņųŅßĻ©∑›≤»§«§Ę§Í§ §¨§ť°Ęņł≥Ť§ňŐ©ņ‹§∑§ŅÕÕ°Ļ§ ™§őį’ĺʧ‚ľÍ§¨§Ī§Ņ°Ę
∂‹¬Űý§≤ū§ň§Ť§Žľ ŐŌÕÕ§ő•«•∂•§•ů°£
ĽĢ¬Ś§Úī∂§ł§Ķ§Ľ§ļ°Ę§Ķ§ť§ňŌ¬ľľ§«§‚Õőľľ§«§‚°Ę§…§Ń§ť§ň§‚∆Žņų§ŗ…Š ◊§Ķ§¨§Ę§Í§ř§Ļ°£

§ľ§“°Ę Ž§ť§∑§ňľŤ§Í∆Ģ§ž§∆§Ŗ§∆§Į§ņ§Ķ§§°£
ѧŌńÍ»÷ ѧ¨£∑ľÔőŗ°Ę•Ķ•§•ļ§Ō£Ī£ĪľÔőŗ§«§Ļ°£
ļŖłň§ň§ §§§‚§ő§‚§ī√Ū ł§ÚĺĶ§Í§ř§Ļ§ő§«°Ę§™Őš§§ĻÁ§Ô§Ľ§Į§ņ§Ķ§§°£
ņĹļÓ≤ŠńݧŌ§≥§Ń§ť§ő•÷•Ū•į§«§īĺ“≤ū§∑§∆§™§Í§ř§Ļ°£
§…§¶§ĺ§īÕų§Į§ņ§Ķ§§°£
§™ľÍ∆Ģ§ž°¶Ľ»Õ—§ň§ń§§§∆
ŅŚņŲ§§§«§≠§ř§Ļ°£ņŲ§√§ŅłŚ§Ō Ņī≥§∑§∑§∆§Į§ņ§Ķ§§°£
° őĘ√Ō§őĽś•∆°ľ•◊§Ō¬—ŅŚņ≠§¨§Ę§Í§ř§Ļ°ň
≤»∂٧ő≤ľ§ §…§ň√÷§§§∆§‚§īÕÝÕ—§§§Ņ§ņ§Ī§ř§Ļ§¨°Ę
įōĽ“§ §…§ő≤ľ§ň…Ŗ§ĮĺžĻÁ§ŌĽ§§ž§ň§Ť§Í°ĘĹż§Ŗ§š§Ļ§§§ő§«§ī√Ūį’§Į§ņ§Ķ§§°£
•’•Ū°ľ•Í•ů•į§ň…Ŗ§Įļ›§Ō°Ę≥ͧͧš§Ļ§§§ő§«°ĘĽ‘»ő§ő≥ͧͼŖ§Š•ř•√•»§ §…§ÚÕ—§§§Ž§»ő…§§§«§Ļ°£
•Ķ•§•ļįžÕų
≤÷…”…Ŗ§≠° 17°Ŗ18cm°ň
•∆°ľ•÷•Ž•Ľ•ů•Ņ°ľĺģ° 23°Ŗ30°ň
•∆°ľ•÷•Ž•Ľ•ů•Ņ°ľ√ś° 30°Ŗ45°ň
•∆°ľ•÷•Ž•Ľ•ů•Ņ°ľ¬Á° 36°Ŗ73°ň
•∆°ľ•÷•Ž•ť•ů• °ľ√ś° 15°Ŗ45°ň
°ľ•÷•Ž•ť•ů• °ľ∆√¬Á° 15°Ŗ91°ň
•ř•√•»ĺģ° 45°Ŗ91°ň
•ř•√•»¬Á° 60°Ŗ121°ň
£ĪĺŲ…Ŗ§≠° 91°Ŗ182°ň
£≤ĺŲ…Ŗ§≠° 182°Ŗ182°ň
£≥ĺŲ…Ŗ§≠° 182x273°ň
Ń“…ŖŚňńŐ
-
 °ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Ř•∆°ľ•÷•Ž•ť•ů• °ľ°°¬Á°°ĶžNo.11 Ń(ņ÷)
6,160ĪŖ(ņ«ĻĢ)
°ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Ř•∆°ľ•÷•Ž•ť•ů• °ľ°°¬Á°°ĶžNo.11 Ń(ņ÷)
6,160ĪŖ(ņ«ĻĢ)
-
 °ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Ř•∆°ľ•÷•Ž•ť•ů• °ľ°°¬Á°°No.4 Ń(ļį)
6,160ĪŖ(ņ«ĻĢ)
°ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Ř•∆°ľ•÷•Ž•ť•ů• °ľ°°¬Á°°No.4 Ń(ļį)
6,160ĪŖ(ņ«ĻĢ)
-
 °ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Ř•∆°ľ•÷•Ž•ť•ů• °ľ°°∆√¬Á°°ĶžNo.11 Ń(ņ÷)
8,250ĪŖ(ņ«ĻĢ)
°ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Ř•∆°ľ•÷•Ž•ť•ů• °ľ°°∆√¬Á°°ĶžNo.11 Ń(ņ÷)
8,250ĪŖ(ņ«ĻĢ)
-
 °ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Ř•∆°ľ•÷•Ž•Ľ•ů•Ņ°ľ°°¬Á°°ĶžNo.11 Ń(ņ÷)
11,330ĪŖ(ņ«ĻĢ)
°ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Ř•∆°ľ•÷•Ž•Ľ•ů•Ņ°ľ°°¬Á°°ĶžNo.11 Ń(ņ÷)
11,330ĪŖ(ņ«ĻĢ)
-
 °ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Ř•∆°ľ•÷•Ž•Ľ•ů•Ņ°ľ°°¬Á°°No.4 Ń(ļį)
11,330ĪŖ(ņ«ĻĢ)
°ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Ř•∆°ľ•÷•Ž•Ľ•ů•Ņ°ľ°°¬Á°°No.4 Ń(ļį)
11,330ĪŖ(ņ«ĻĢ)
-
 °ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Řłľīō•ř•√•»°°ĺģ°°No.4 Ń(ļį)
20,350ĪŖ(ņ«ĻĢ)
°ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Řłľīō•ř•√•»°°ĺģ°°No.4 Ń(ļį)
20,350ĪŖ(ņ«ĻĢ)
-
 °ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Řłľīō•ř•√•»°°ĺģ°°ĶžNo.11 Ń(ņ÷)
20,350ĪŖ(ņ«ĻĢ)
°ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Řłľīō•ř•√•»°°ĺģ°°ĶžNo.11 Ń(ņ÷)
20,350ĪŖ(ņ«ĻĢ)
-
 °ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Řłľīō•ř•√•»°°¬Á°°No.4 Ń(ļį)
30,580ĪŖ(ņ«ĻĢ)
°ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Řłľīō•ř•√•»°°¬Á°°No.4 Ń(ļį)
30,580ĪŖ(ņ«ĻĢ)
-
 °ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Řłľīō•ř•√•»°°¬Á°°ĶžNo.11 Ń(ņ÷)
30,580ĪŖ(ņ«ĻĢ)
°ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Řłľīō•ř•√•»°°¬Á°°ĶžNo.11 Ń(ņ÷)
30,580ĪŖ(ņ«ĻĢ)
-
 °ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Ř≤÷…”…Ŗ§≠ No.5 Ń
1,870ĪŖ(ņ«ĻĢ)
°ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Ř≤÷…”…Ŗ§≠ No.5 Ń
1,870ĪŖ(ņ«ĻĢ)
-
 °ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Ř≤÷…”…Ŗ§≠ No.6 Ń
1,870ĪŖ(ņ«ĻĢ)
°ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Ř≤÷…”…Ŗ§≠ No.6 Ń
1,870ĪŖ(ņ«ĻĢ)
-
 °ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Ř≤÷…”…Ŗ§≠ No.7 Ń
1,870ĪŖ(ņ«ĻĢ)
°ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Ř≤÷…”…Ŗ§≠ No.7 Ń
1,870ĪŖ(ņ«ĻĢ)
-
 °ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Ř•∆°ľ•÷•Ž•Ľ•ů•Ņ°ľĺģ No.3 Ń
3,080ĪŖ(ņ«ĻĢ)
°ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Ř•∆°ľ•÷•Ž•Ľ•ů•Ņ°ľĺģ No.3 Ń
3,080ĪŖ(ņ«ĻĢ)
-
 °ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Ř•∆°ľ•÷•Ž•Ľ•ů•Ņ°ľĺģ No.5 Ń
3,080ĪŖ(ņ«ĻĢ)
°ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Ř•∆°ľ•÷•Ž•Ľ•ů•Ņ°ľĺģ No.5 Ń
3,080ĪŖ(ņ«ĻĢ)
-
 °ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Ř•∆°ľ•÷•Ž•Ľ•ů•Ņ°ľ√ś No.1 Ń
6,160ĪŖ(ņ«ĻĢ)
°ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Ř•∆°ľ•÷•Ž•Ľ•ů•Ņ°ľ√ś No.1 Ń
6,160ĪŖ(ņ«ĻĢ)
-
 °ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Ř•∆°ľ•÷•Ž•Ľ•ů•Ņ°ľ√ś No.2 Ń
6,160ĪŖ(ņ«ĻĢ)
°ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Ř•∆°ľ•÷•Ž•Ľ•ů•Ņ°ľ√ś No.2 Ń
6,160ĪŖ(ņ«ĻĢ)
-
 °ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Ř•∆°ľ•÷•Ž•Ľ•ů•Ņ°ľ√ś No.3 Ń
6,160ĪŖ(ņ«ĻĢ)
°ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Ř•∆°ľ•÷•Ž•Ľ•ů•Ņ°ľ√ś No.3 Ń
6,160ĪŖ(ņ«ĻĢ)
-
 °ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Ř•∆°ľ•÷•Ž•Ľ•ů•Ņ°ľ√ś No.5 Ń
6,160ĪŖ(ņ«ĻĢ)
°ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Ř•∆°ľ•÷•Ž•Ľ•ů•Ņ°ľ√ś No.5 Ń
6,160ĪŖ(ņ«ĻĢ)
-
 °ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Ř•∆°ľ•÷•Ž•Ľ•ů•Ņ°ľ√ś No.7 Ń
6,160ĪŖ(ņ«ĻĢ)
°ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Ř•∆°ľ•÷•Ž•Ľ•ů•Ņ°ľ√ś No.7 Ń
6,160ĪŖ(ņ«ĻĢ)
-
 °ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Ř•∆°ľ•÷•Ž•Ľ•ů•Ņ°ľ¬Á No.2 Ń
11,330ĪŖ(ņ«ĻĢ)
°ŕŃ“…ŖŚňńŐ°Ř•∆°ľ•÷•Ž•Ľ•ů•Ņ°ľ¬Á No.2 Ń
11,330ĪŖ(ņ«ĻĢ)
- Ńį§ő•ŕ°ľ•ł
- 71嶅 √ś 1-20嶅
- ľ°§ő•ŕ°ľ•ł