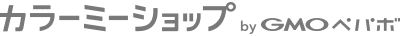- ホーム
- > 陶磁器(やきもの)2
- > 瀬戸焼

瀬戸焼
愛知県にある一大窯業地・瀬戸。
現在、一般に焼きもののことを「せともの」と呼びますが、
その「せと」とは、瀬戸のことを指します。
瀬戸市周辺では、平安時代中期から焼きもの作りが行われてきたと言われ、
日本の最も古い産地の一つです。
長い歴史の中で一貫して陶器が作られてきましたが、
江戸時代末期の19世紀初頭に、肥前(現在の佐賀県)から磁器の生産技術が持ち込まれ、
これを契機に磁器の生産が活発になります。
当時の瀬戸では、陶器は本来の仕事である「本業焼」、新たに入ってきた磁器は「新製焼」と呼ばれましたが、
急速に「新製焼」が広まっていきました。
そして、明治・大正期の工業技術の導入、戦後の高度成長を経て、
瀬戸は、工業製品から雑器、個人作家の器まで、あらゆる焼きものが作られる、
一大窯業地として発展しました。
一里塚本業窯
そんな瀬戸の土地で、今も手仕事で陶器作りに取り組み、
窯名に「本業」が入る窯元が2軒あります。
「瀬戸本業窯」と「一里塚本業窯」です。

▲一里塚本業窯の登り窯(現在は使われていない)
瀬戸本業窯は、江戸時代から続く300年の歴史を誇り、
柳宗悦らをはじめとした民藝同人も関わった、瀬戸の民芸を代表する窯元です。
現代は7代目、8代目後継が中心となって窯を営みます。
一里塚本業窯は、瀬戸本業窯から分家して始まった窯元です。
現在は、2代目の水野雅之さんが一人、窯を営んでいます。
水野雅之さんは、瀬戸本業窯で修行、一職人として働いた後、家の窯を継承。
職人時代には、1日に200個も300個も湯呑をロクロ挽きしたそうで、
繰り返しの仕事によって、技術を身につけたそうです。
ろくろ仕事の様子を見せていただきました。
手早く、湯呑を作っていきます。

出来上がりのサイズを確認しなくても、ぴったりと揃います。
繰り返しの仕事で身につけた技術です。
口の部分は、わずかに外側に反らされていて、
口当たりがよくなるように考えられています。
繊細な技術が要求される仕事です。
手に馴染む程よい重さと、手に取った時の安心感があり、
水野さんのロクロ技術の高さが感じられます。
瀬戸焼の灰釉陶器
瀬戸の伝統的な焼きものといえば、灰釉(かいゆう)陶器です。
日本で最初に生まれた施釉陶器であり、瀬戸焼の代名詞と言えます。
現地で採れる、鉄分の少ない白い粘土を生地に用い、
灰釉と呼ばれる、木の灰と長石を原料にした釉薬をかけただけ。
温かみのある柔らかな黄色が生まれます。

表面には「貫入(かんにゅう)」と呼ばれる微細なヒビがあります。
焼成時に自然に生まれるもので、無地のうつわに表情が生まれます。
この貫入には、使い込むほどに色が沈着し、これが味わいとなります。
育てる器といってもよいでしょう。
手しごとでは、瀬戸伝統の灰釉陶器を中心に、
同じく伝統の鉄釉(飴釉)や黄瀬戸の仕事などもご紹介しています。
手しごとが紹介する瀬戸焼
手しごとの発起人であり、鎌倉・もやい工芸の創業者である故・久野恵一は、
伝統的な瀬戸の灰釉陶器を受け継ぎ、現代の暮らしでも活きる優れた製品作りに、
水野雅之さんとともに取り組みました。
例えば、骨董店で見つけた瀬戸の焼き物を見本に製作を依頼した、
「女碗」「男碗」がその一つ。

シンプルな形ですが、すっきりと直線的に立ち上がる姿や、
高台の大きさ、重さなど、絶妙なバランスが取られており、
水野さんのロクロ技術の高さがわかります。
手しごとでは、「黄瀬戸(きせと)」の仕事をご紹介しています。
黄瀬戸は、安土桃山期頃から見られる釉薬で、
灰釉に鬼板(鉄分を含んだ土)をわずかに混ぜたもの。

灰釉のような貫入はあまり生まれず、マットな風合いで、
釉薬の色の濃淡が生まれることで、味わいのある表情が特徴です。
一般的な黄瀬戸は、表情の変化を強調したものが多いですが、
今回は、普段使いで使っていただくことを考え、
あえて表情を抑えるように調整していただきました。

結果、灰釉陶器のシンプルですっきりした印象を保ち、
水野雅之さんの作る形の良さを感じられるものになったと思います。
毎日の食卓で活躍してくれて、使い込むほどに味わいが生まれる、
瀬戸焼のうつわ。ぜひ、お試しください。
瀬戸焼
-
 【瀬戸焼・一里塚本業窯】黄瀬戸一輪挿し 織部
4,400円(税込)
【瀬戸焼・一里塚本業窯】黄瀬戸一輪挿し 織部
4,400円(税込)
-
 【瀬戸焼・一里塚本業窯】黄瀬戸角ぐいのみ
SOLDOUT
【瀬戸焼・一里塚本業窯】黄瀬戸角ぐいのみ
SOLDOUT
-
 【瀬戸焼・一里塚本業窯】灰釉フリーカップ
SOLDOUT
【瀬戸焼・一里塚本業窯】灰釉フリーカップ
SOLDOUT
- 前のページ
- 3商品中 1-3商品
- 次のページ