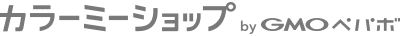- ホーム
- > 陶磁器(やきもの)2
- > 丹波焼

丹波焼
兵庫県丹波篠山市にある立杭(たちくい)。
小高い山に挟まれた狭い山あいの土地で、平安時代末期から焼き物が作られてきたと言われます。
丹波焼(丹波立杭焼)は、その歴史の古さから「日本六古窯」にも数えられます。
古くは甕、すり鉢といった大物の雑器が作られましたが、
京都や大阪といった大都市に近い立地もあり、
江戸時代から、茶陶や民衆が使う生活陶器の生産が盛んになります。
しかし明治以後は、磁器などいわゆる瀬戸物の流通に押され、衰退していきました。

△斜面に沿って築かれた丹波の登り窯(兵庫県の重要民俗資料に指定)
地元で採れる鉄分を多く含んだ赤黒い土を用い、
穴窯と呼ばれる原始的な登り窯で焼かれる、素朴な焼き物であった丹波焼。
そこに美を見出し、広く紹介したのが、柳宗悦らをはじめとする民藝運動です。
そして、衰退した状況を打破するため、新しい日用品への道を開く取り組みが始まります。
民藝運動を主導した陶芸家・河井寛次郎の弟子である
奥田康博(三重県で神楽の窯を築窯、いろは窯服部さんの師匠)や生田和孝らは、
丹波焼の再興に取り組みました。
特に生田は、中国や朝鮮の古陶磁を手本に、鎬(しのぎ)や面取りといった技法や、
丹波焼特有の穴窯での焼成によって、柔らかな白に発色する糠釉を導入するなど、
丹波の風土に根ざし、丹波焼ならではの特徴や技術を残しつつも、
近代的な生活に即した新作づくりに取り組みました。
彼らの取り組みは、現代の丹波焼に活かされています。
丹波焼・俊彦窯(清水俊彦)
手しごとは、立杭で窯を営む清水俊彦さんのうつわをご紹介しています。

清水俊彦さんは高校を出てすぐ、生田和孝に師事。
10年以上にわたり職人として支えました。
生田窯で作られていた生活雑器の一部は、清水さんが受け継いでいます。
清水さんの仕事からは、長年の職人経験を象徴するような、熟練の技術が感じられます。
鎬や面取など、技法自体はシンプルなものですが、
長年に渡って培った技からこそ生まれる良さがあります。
骨格のある形も清水さんが持つ技術と感覚から生まれるものです。

糠釉の白は、釉薬の性質上発色が安定しないため、現地で一つ一つ眼を通して選びます。
そのため、入荷数はそれほど多くありません。
丹波黒とも呼ばれる丹波焼ならではの特徴的な黒釉は、
漆黒ともいうべき深い黒色で、独特の魅力を放ちます。
清水さんは、丹波の古作の再現にも取り組みます。
海老徳利とよばれる、生き生きとした海老が描かれた徳利です。
見事な技です。

手しごとでは、丹波焼の持つ伝統とその魅力をお伝えすべく、
清水さんが取り組む、日常に寄り添う器を中心にご紹介しています。
丹波焼
-
 【丹波焼・俊彦窯】5寸平鉢 灰釉
3,410円(税込)
【丹波焼・俊彦窯】5寸平鉢 灰釉
3,410円(税込)
-
 【丹波焼・俊彦窯】4寸皿 しのぎ 黒釉
SOLDOUT
【丹波焼・俊彦窯】4寸皿 しのぎ 黒釉
SOLDOUT
-
 【丹波焼・俊彦窯】5.5寸鉢 糠釉 しのぎ
SOLDOUT
【丹波焼・俊彦窯】5.5寸鉢 糠釉 しのぎ
SOLDOUT
-
 【丹波焼・俊彦窯】6寸鉢 糠釉 櫛目
SOLDOUT
【丹波焼・俊彦窯】6寸鉢 糠釉 櫛目
SOLDOUT
- 前のページ
- 4商品中 1-4商品
- 次のページ